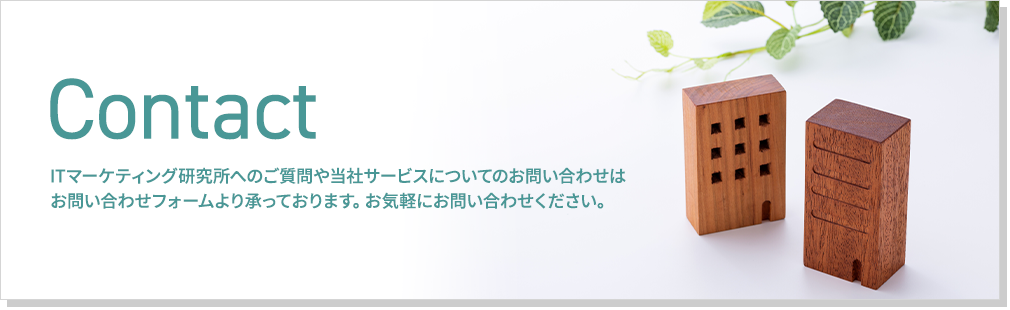BtoC拡大に向けHP駆使したウェブ戦略展開
創業当初は銘木業として床の間や和室部材を製造していたが、住宅様式の変化を見据え、いち早く化粧材の製材業へと事業を転換したドリーミィ大和。
原口直樹社長の「木の価値を守り、未来へ届けるために」という想いのもと、燻煙熱乾燥技術を核に独自のブランドを築き上げてきた。同社が現在目指しているのが、BtoC向け事業の拡大だ。
製材から乾燥・加工までを地産地消で

──事業内容は?
原口 床や天井など、建築の中でも目にする機会の多い化粧材を中心に加工・販売しています。
私たちはもともと銘木業として産声を上げた会社ですが、床の間がない家が増えるなど、住宅様式の変化に伴い銘木の需要が減少したことを受けて、新たな道として製材業をはじめました。
現在は、木材の伐採時や製材過程で出る端材を燃料とした、燻煙熱処理で乾燥させた化粧材「くんえん杉」をオリジナル商品の「燻─IBUSHI─」として販売しています。
また、住宅や店舗の床材・壁材だけでなく、近年では端材を活用した木工小物やサウナ小屋など、消費者向け商品の展開にも取り組んでいます。
──強みは?
原口 当社にしかできない高度な燻煙熱乾燥処理技術などを駆使した品質の高さです。銘木業時代に培った技術で、節の大きさや木目・色のそろえ方を一つ一つ確認しているので、施工現場では「貼りやすく、仕上がりがきれい」と評価をいただいています。また、業界では珍しい取り組みとして、化粧材の全量含水率検査を行っています。これによって当社の製品は、乾燥不足による反りや割れが少なく、職人さんや元請け会社さまから「化粧材を使うならドリーミィ大和のものがいい」とご指名をいただくことも増え、取引先が広がっています。

──燻煙熱乾燥という独自技術を開発された背景は?
原口 木材の乾燥といえば化石燃料を使ったボイラーによる機械乾燥が主流なのですが、燃料費や環境負荷などの課題があります。そこで当社が取り組んだのが、炭をつくるための窯で間伐材や使い道のない原木を燃料にした燻煙熱乾燥でした。試行錯誤を重ねて、内部割れが少なく、木の風合いをそのまま保ちながら乾燥できる独自の技術を確立させました。燻煙熱乾燥は、環境に優しく、林業の現場で扱いに困っていた曲がり材や放置材を燃料として買い取るので、山の手入れという意味でも役立っています。
──今後の展望は?
原口 BtoBだけでなく、BtoCにも力を入れていこうと考えています。工務店から当社の製品を使いたいとご指名いただけるよう、営業活動はもちろんのこと、ブランディングや認知度向上にも注力しています。
また、一般消費者向けにもDIYをするための端材やウッドスピーカーなどの木製品、高価格帯ではサウナ小屋など、木の魅力を届けたいと思っています。価格帯も低・中・高と分けて、木が好きな方であれば誰でも手に取れるラインアップを考えています。
BtoC向けの発信基地として

──これまでHPをどう活用してこられましたか。
原口 税理士法人南九州総合会計信和オフィスさんからの紹介でアイ・モバイル社の『BESTホームページ』を使い始めたのは10年以上前のことです。当時は最低限の企業情報を載せただけのシンプルなものでした。問屋経由の取引が多かったことから、一般消費者などに向けた発信の必要がなかったため、HPはそれほど重要視していなかったのです。
ですが、今後BtoC事業を拡大しようと考えたとき、工務店や一般のお客さまにブランドを知っていただくためには、よりHPを有効に活用する必要があると感じ、リニューアルに踏み切りました。ちょうど木材加工現場のドローンによる撮影の準備が整ったことも後押しとなりました。

──リニューアル時に留意したことは何ですか。
原口 当社の魅力を正しく、そしてかっこよく見せることです。具体的には、私たちの強みでもある木材加工技術や職人の目利き、燻煙熱処理加工など製品の魅力を一般のお客さまや工務店さんに分かりやすく伝えることを心がけました。また、当社のの製材製品を使った施工事例の掲載記事、オンラインショップなど、BtoC向けのコンテンツを強化しました。いずれにせよ、『BESTホームページ』を引き続き活用したのは、自社でページを増やしたり編集したりといった作業がしやすいというメリットを、より生かせそうだと考えたからです。
〝企業の顔〟として活用
── HP活用の現状は?
原口 リニューアル後は、工務店さんや建築家さんへの営業時に必ずHPを見ていただくようにしています。メールの署名にもリンクを入れて、「これが私たちの顔です」と堂々と言えるようになりました。また、端材や小物、サウナ小屋といった新商品も、HP上において写真と説明入りで発信しています。当社の製品を使ったときのイメージが分かるように、施工事例も工務店さんから写真をいただき、随時追加するようにしました。こうした更新作業も自社で簡単にできるシステムなので、営業活動の〝後押し〟としてフルに活用できています。
──今後のHP活用の展望は?
原口 ひとつには、製造工程ごとの動画をカテゴリー別に掲載したいと思っています。工場にはいくつもの工程があり、その一つ一つが当社の価値そのものなので、見ていただければ、「こんな技術があるんだ」と感じてもらえるはずです。
HPは、単なる情報サイトではなく、会社の看板だと考えています。以前のHPは、単なる〝第3の営業マン〟としての位置付けでしたが、今やウェブ上での発信は企業ブランディングの核となっています。ウェブを通してもっと木の魅力を届け、ドリーミィ大和という名前を知っていただく……そのための挑戦は、これからが本番だと思っています。
(取材協力・税理士法人南九州総合会計 信和オフィス)
ドリーミィ大和株式会社
住所:〒891-1101 鹿児島県鹿児島市花尾町1302
URL:https://www.dreamy-y.jp/
(インタビュー・構成/アイ・モバイル 株式会社)
株式会社TKC発行のビジネス情報誌「戦略経営者」に掲載された連載記事を掲載しております。
この記事への感想やご意見、サービスに関するご質問がありましたら、下記ボタンよりお問合せください。
ホームページの制作に関するご相談・ご質問は下記Smartpageサイトよりお問い合わせください。